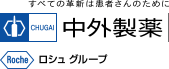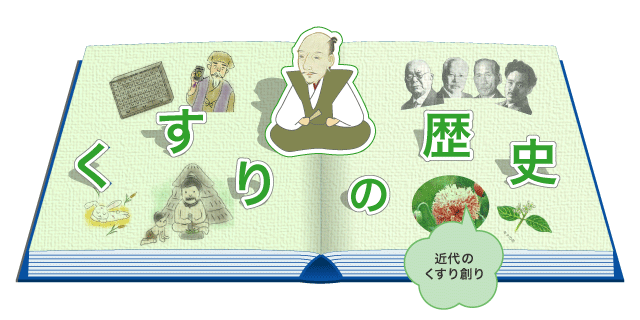
近代のくすり創り
有効成分の発見と分離
近代の薬の多くは、植物・動物・鉱物などに含まれる有効成分を抽出し、化学的に変化を加えたり、化学合成することによって現在まで創り続けられてきました。
ケシの実からモルヒネ
西洋でも東洋でも、ケシの種子や汁は昔からさまざまな目的に使われてきました。

人類にとって最も古い医薬の記録であるとされた「エーベルス・パピルス」(紀元前1550年頃)には、ケシのチンキ処方※が赤ちゃんの夜泣きを治すと記録されています。
※チンキ:生薬をエタノールと精製水の混合液に浸してつくる液状の製剤
また、ケシの種子は栄養源として、食用にも利用されていました。その後、ケシの未熟果を傷つけた時に分泌する乳液を乾燥したものから、阿片が採取され、薬として使われていました。
- チンキ用語解説を開く
- 生薬をエタノールと精製水の混合液に浸してつくる液状の製剤
1804年、ドイツの薬剤師F. W .セルチュルナーが、阿片から有効成分を取り出すことに成功しました。この有効成分は、眠りの女神モルフィウスの名にちなんでモルヒネと名付けられました。
有効成分を純粋な結晶として取り出すことができたことにより、近代薬学の幕開けとなりました。この発見に刺激され、他の薬学者たちにより古来使われてきた薬草や有毒植物などから、有効成分を取り出す研究が一斉にはじまりました。モルヒネは、現在もがん患者さんの痛みを緩和するなどの役割をはたしています。
ヤナギの樹皮からアスピリン
ヤナギの樹皮は古代ギリシャ時代から痛風、神経痛などに使われてきました。紀元前のギリシャの医師、ヒポクラテスはヤナギの樹皮を鎮痛・解熱に使っていたと伝えられています。日本でも、ヤナギには鎮痛作用があり、歯痛に効果があると考えられ、つまようじとして使われていました。
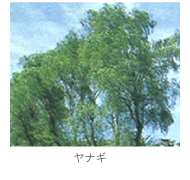
1763年、イギリスの神父E .ストーンは、ヤナギの樹皮の抽出エキスが、悪寒、発熱、腫脹などに強い効果があることを発見し、ヤナギの学名サリュックに因みサリシンと名づけました。1838年にはサリシンを分解してサリチル酸が得られることも判明しました。
サリチル酸はリウマチの治療などに使用されていましたが、苦味が強く、胃腸障害などの副作用もありました。ドイツの化学者F .ホフマンは、リウマチを患う父をサリチル酸の副作用から救うべく開発に没頭し、1897年に副作用の少ないアセチルサリチル酸(アスピリン)を合成するのに成功しました。
近代の薬の開発には、このように副作用を減らし、効果を高めていくような研究が行われていました。
キニーネ
キニーネは抗マラリア薬で、熱を下げ、痛みを抑える解熱・鎮痛作用もあります。アカネ科の植物キナの樹皮に含まれています。

南米の原住民は、古くからアンデスの高地に生えるキナの樹皮がマラリアに効くと知っていたといわれています。1630年頃には、イエズス会の宣教師がキナの樹皮を使って治療を行っていたそうです。
キナの有効成分「キニーネ」は、1820年、フランス・パリ薬学校のP .J .ペルティエとJ .カヴァントゥによって抽出されました。キニーネは今でもマラリア薬として使用されるほか、強壮効果があることから、海外では清涼飲料水として飲まれているトニック・ウォーターにも使われています。